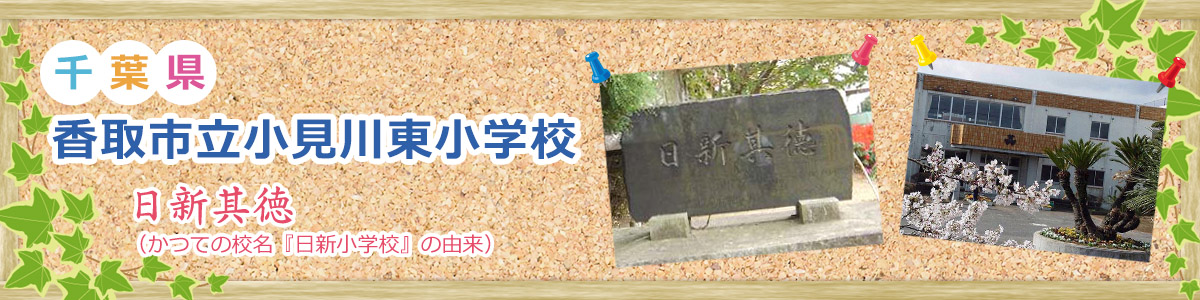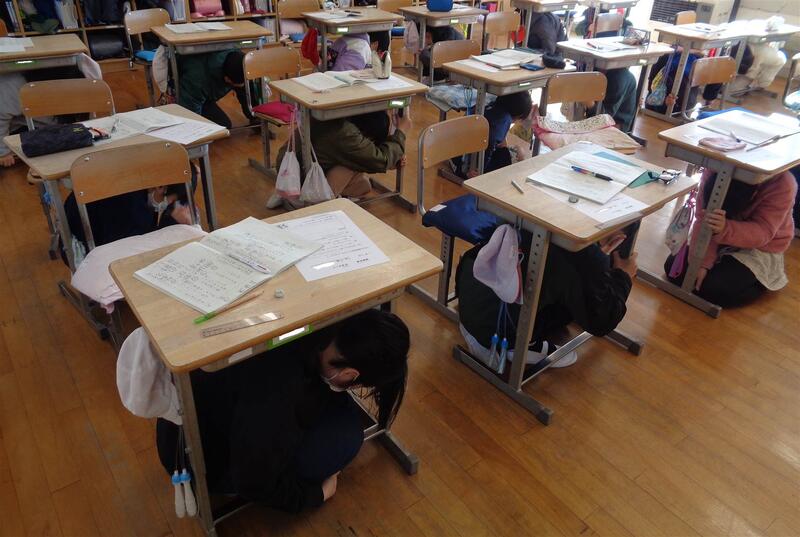文字
背景
行間
東っ子日誌
新着
昨日は大雪のため休校になりました。また、本日は10時登校で3時間目からの授業に変更させていただきました。保護者の皆様、ご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。
東っ子たちは久しぶりの雪に大はしゃぎ!銀世界に笑顔の花が咲きました。
今年度最後の「詩の暗唱」がスタート!初日は4年生が好スタートを切りました。4年生の課題は「吾輩は猫である」です。
{{item.Plugin.display_name}}
{{item.Topic.display_publish_start}}
{{item.RoomsLanguage.display_name}}
{{item.CategoriesLanguage.display_name}}
{{item.Topic.display_summary}}
アクセシビリティ
文字
背景
行間
カウンタ
3
6
4
0
1
3
3
家庭でできる学習サイト
「ちばっ子チャレンジ100」
(千葉県教育委員会:学習資料)

子供の学び応援サイト(文部科学省)

NHK For School(NHK)
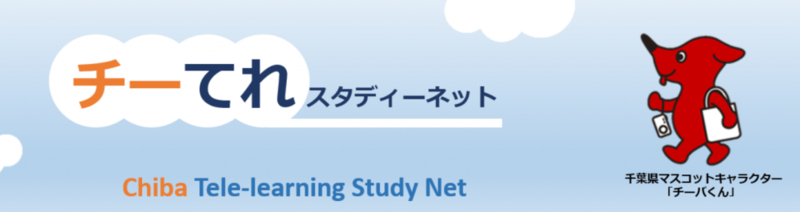
チーてれスタディーネット
(千葉県教育委員会)
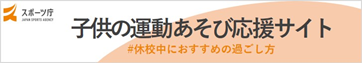
子供の運動あそび応援サイト
(スポーツ庁)
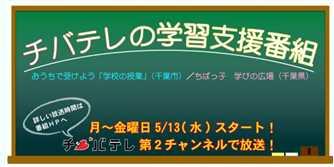
チバテレの学習支援番組

家庭での体育、保健体育の
学習コンテンツ参考例
県内トップ・プロによる家庭(室内)で出来る運動動画集
リンク