文字
背景
行間
学校から
香取市教育委員会学校訪問 10月29日(木)
金子教育長はじめ教育委員ならびに教育委員会の方々が来校され、児童の様子及び施設の状況を視察されました。短時間ではありましたが、5校時の授業を参観していただきました。とても落ち着いて授業を受けているとの感想をいただきました。今後とも、わらびが丘小学校に対するサポートをよろしくお願いいたします。 (文責 海寳)
もうすぐ80,000カウント 10月28日(水)
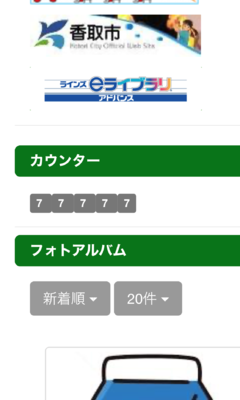
各月ごとのカウント数の推移は次の通りです。
7月1日 9,687
8月1日 24,416 (+14,729)
9月1日 42,436 (+18,020)
10月1日 61,851 (+19,415)
本ホームページは、保護者、地域の方々、学校関係者、旧福田・神南小卒業生、旧福田・神南で御退職された先生ならびにかつて在籍された先生など、多くの方が閲覧されています。また、以前「学校のホームページを見たのですが」と、ある業者の方から電話があったこともあります。
学校関係だけでなく、様々な外部の方も閲覧されているということで、内容についても責任をもってアップしなければという認識を強く持っています。
今後も、「開かれた学校」をめざして学校の様子を発信していきたいと考えております。ぜひ、楽しみにしながら見ていただければ幸いです。 (文責 海寳)
網戸が設置されました。 10月28日(水)
コロナウイルス対策補助金を使って、校舎のすべての窓に網戸を設置しました。感染予防の飛沫対策では、教室の2方向の窓を開けることになっています。しかし、これまでは網戸がなかったために、蜂などの虫が入ってくることがありました。先月には、体育館の裏の軒に、大きなスズメバチの巣があり、駆除してもらいました。授業中にスズメバチが入ってきたらたいへんです。そこで、校舎のすべての窓に網戸を設置しなければならないと考えました。
じつは、旧佐原三中の窓は、成田空港の騒音対策の関係で特殊な窓枠になっています。普通のサッシならば、網戸をはめ込むだけで済むのですが、本校は網戸をはめ込むためのレールを設置しなければなりませんでした。グラウンド側の3階までのすべての教室の窓が対象です。業者の方には、毎日暗くなるまで作業をしていただき、短期間で据え付けが完了しました。道路側は通常のサッシ枠なのですが、網戸用のレールがなく、すべて取り付けてもらいました。先日工事が完了し、やっと安心して過ごせるようになりました。 (文責 海寳)
お詫び(と言い訳) 10月21日(水)
運動会の写真のアップを楽しみに待っていた皆様へのお詫び(と言い訳)です。
毎日ホームページへの記事のアップを担当しています私(校長)は、本日、午前と午後に別々の出張がございまして、そのすき間を使って「わらびっ子 スポーツDAY④」を着々と作成していたのですが、パソコンの不調により写真の貼り付けをしようとするとエラーの連続で、泣く泣く本日のアップを断念いたしました。楽しみに待っていた皆様、何度も何度もスマホでチェックされていた方も多かったのではと推察します。
明日は、必ず復旧させ、写真をアップさせますので、明日を楽しみにしていてください。午前中にはなんとか一つ記事をアップします。しばしお待ちください。
苦渋の決断ですが・・・ 10月18日(日)
雨は上がりました。しかし、昨日一日しっかり降っていたので、グラウンドは全体的に水を含んだスポンジのようにやわい状態です。加えて応援席はじめトラック周りは水没しています。
苦渋の決断ですが、本日も延期とします。楽しみにしていた保護者の皆様には残念な結果となりました。学校の様子も含めて、子供たちの様子をぜひご覧いただけたらと準備していただけに、私たち教職員も残念な気持ちでいっぱいです。
「わらびっ子 スポーツDAY」は、天候とグラウンド状況をみて、明日以降の平日に開催します。子供たちの様子をホームページにできるだけアップしますので、そちらを楽しみにしていてください。 (文責 海寳)
















