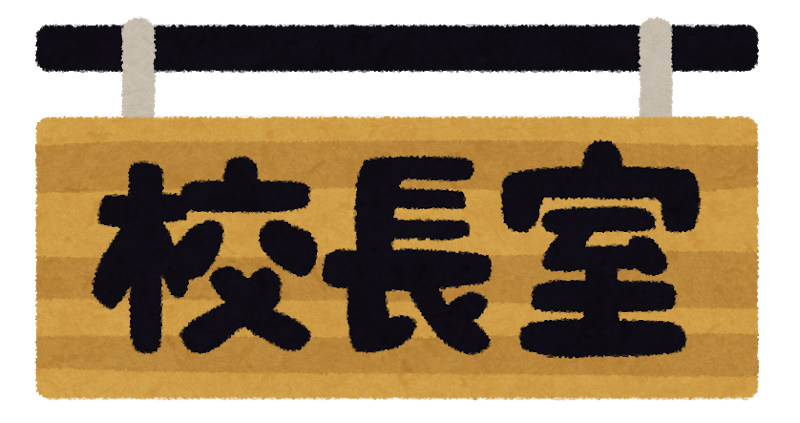
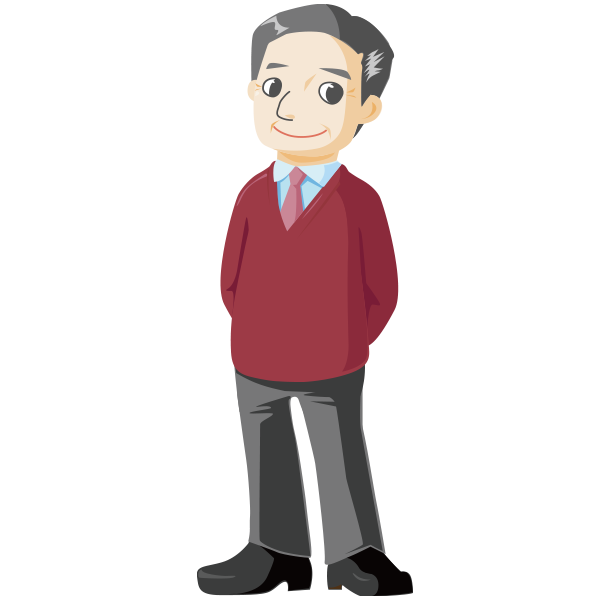

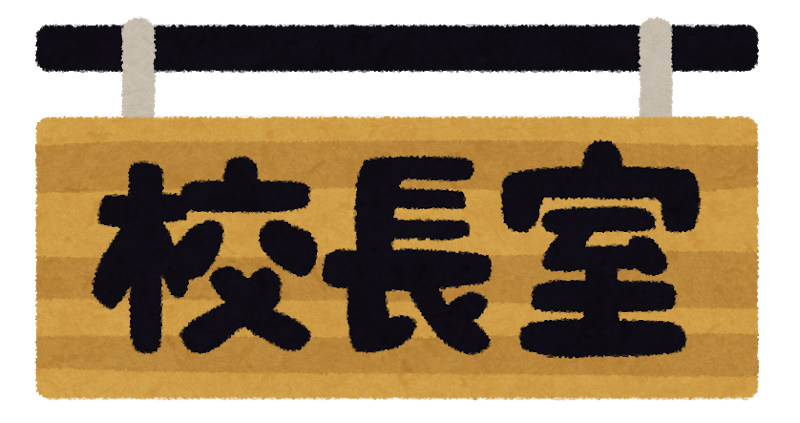
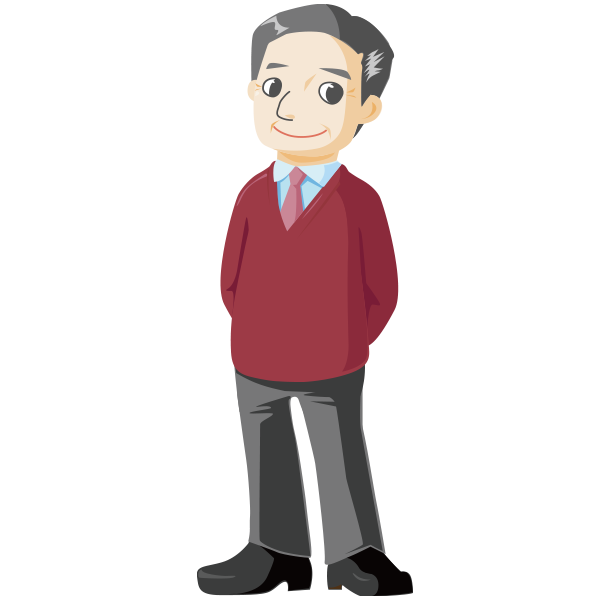
今日(1/22)、中央小学校に一人の男性が訪ねてきました。
校長が対応したところ、「小見川陣屋のことを調べているので、学校の敷地内にあるという陣屋に関する碑を見せてほしい」とのことでした。埼玉県から電車を乗り継いで来たそうです。
陣屋の意味合いは時代とともに変化していますが、江戸時代につくられた小見川陣屋は藩の政治拠点を担い、藩主の屋敷でもあったそうです。1724年に4代藩主 内田正親が小見川周辺に一万石を与えられ、小見川に居住が定められました。小見川陣屋には堀や土塁が築かれ、内田氏支配は明治維新まで続きました。
そのような歴史がある土地に、明治8年以降150年以上にわたってある学校が現在の小見川中央小学校です。・・・と、ここまでは知っていましたが、肝心の埼玉県から訪ねてきた男性が見たい碑についてはわかりませんでした。わざわざ埼玉県から来ていただいた方に、「わかりません」と帰ってもらうのは申し訳ないので、小見川陣屋址に関する説明の看板や中央小にあるいくつかの石碑をご案内しました。
中央小の校庭にはいくつかの石碑があります。これを機に、あらためて見てみました。とても大きな石碑が3つあります。
学校の玄関の近くにある大きな石碑に書かれているのは、「 正 強 朗 」 です。
昨年の創立記念式で児童たちに説明しましたが、中央小の校医を50年以上務めた初代同窓会長 本多 元俊 先生が書いた言葉で、「正しく 強く 朗らかに」 と、人としての生き方を示してくれています。
中央小のシンボルツリーである「くすのき」の近くにある石碑(創立80周年記念碑)には、金森 徳次郎 先生(憲法学者、政治家)の書で「修道之謂教」 と書かれています。孔子の「中庸」にある言葉で、「人としての正しい道を、毎日繰り返して身につけることが、本当の勉強です」という意味です。今年の創立記念式で児童たちに話そうと思っていますが、少し難しいでしょうか?
また、体育館の脇には、「修道百年」 と書かれた石碑があります。80周年記念碑の「修道之謂教」を受けての100周年記念碑で、建てられたのは100周年の2年後のようです。当時の校長 石橋 喜逸 先生の書です。
児童が帰ってからの職員打合せで、小見川陣屋の話を本校の職員にしたところ、石碑について調べてくれた職員がいて、その石碑はなんと!中央小の「くすのき」と「修道之謂教」と書かれた石碑の間にある大きな石であることがわかりました。石には読み取れる字もなく「どうしてこんな大きな石がここにあるのだろう?」という程度に思っていた石が、小見川陣屋の石碑だなんて・・・
埼玉県から訪ねてきてくださった方には申し訳なかったですが、勉強になる一日でした。次に小見川陣屋址を訪ねてきてくださる方がいたら、ご案内できるようにします。
本日(12月12日)の千葉日報に、11月28日(金)に本校体育館で実施した「地域高齢者交流会」の記事が掲載されました。(ぜひ、ご覧ください。)この交流会は、小見川中央地区社会福祉協議会の皆様のお力をいただき開催しており、中央小の3年生が歌やダンスを披露し、ゲームなどを一緒に行い交流をもつものです。
3年生の児童たちは、「どうしたら、来てくれた方々に喜んでもらえるか」を真剣に考え、計画しました。私も児童たちがどんな「おもてなし」をできるのか、少し心配しながらも楽しみにしていましたが、高齢者の皆様にとても喜んでいただき、児童たちも大きな満足感を得ることができたことが、笑顔いっぱいの会場の様子から感じることができました。
12月16日発行予定の小見川中央小学校こども新聞「くすのは」に掲載される3年生の児童の作文の一部を紹介します。
みんなで作ったけん玉でたくさん遊び、地域のみなさんが、「おもしろいね」と言ってくれたことが一番うれしかったです。折り紙で作ったおみやげも喜んでくれました。
交流会では、つえをついている人や耳が聞こえにくい人もいました。そのような高齢者のみなさんと遊ぶことができてうれしかったです。この日のことをずっとおぼえておこうと思います。
普段、お年寄りと接することがほとんどない児童も多くいますが、高齢者の皆様の優しさに触れたり、一生懸命に準備したことを感謝されたりと、児童たちも大きく成長することができた一日となりました。これからも児童たちの思いやりの心を育てていきたいと思います。
本日(12月4日)、快晴の下、小見川中央小学校マラソン大会が開催されました。
低学年は800m、中学年は1200m、高学年は1500mの距離を、各学年男女別に走り、10位までに入った児童には「賞状」が、そして完走者全員に「完走証」が授与されます。
このマラソン大会に向けて、児童たちは「あおぞらタイム」のマラソン練習に10月20日から取り組んできました。また、個人的に練習を積んでマラソン大会に臨んだ児童も多くいました。
開会式で校長から話したのは、マラソンが好きな児童や得意な児童ばかりではないことにふれ、「好きではないことや苦しいことから逃げずにチャレンジしてきた人は立派です!」ということ。また、「入賞する」とか「1位になる」だけがマラソン大会の目標ではなく、例えば、「歩かないでゴールする」も立派な目標であること、そして何より「『自分に負けない』ということを全員の目標にして、今日できる『自分の最高の走り』を目指そう!」と話しました。
そして本番・・・、各レースでは自分の最高の走りをしようと必死に頑張る姿がたくさん見られました。
今年も、ガムシャラに走る児童たちの姿に圧倒され、感動しました!
自分に負けず、苦しいことから逃げない中央小の児童たちは、本当に素晴らしいと思います。
児童たちの安全を見守り、声援を送っていただいた保護者の皆様、地域の皆様のおかげで、安全で感動のあるマラソン大会を実施することができました。ありがとうございました。
「人はなぜ勉強するのか?」 第3弾です。
「勉強する」と「学ぶ」では意味合いが異なりますが、中央小の4年生が「人はなぜ学ぶのか?」をテーマとして、自分の考えを単作文にまとめる学習をしましたので、抜粋して紹介します。
〇人がなぜ学ぶのかは、自分を見つけるためだと思います。ぼくは学校へ通ってから自分を見つけられました。自分を見つけるというのは、自分の楽しいことや悲しいことがわかってくるということで、自分を見つければ、本当にやりたいこと、好きなことが見えてくると思います。
「学校(中央小)で自分を見つけられた」ってすごいです。校長として、とても嬉しい作文ですね。今の自分も、学び続けるとまた変わっていくのでしょうね。
〇ぼくがいつも勉強しているのは、将来の夢を叶えるためです。子どもの時は自分ができるかぎりの勉強をすることが大切だと思いました。大人になっても努力し続けます。人生は自分で決めるものなので、ぼくは将来の夢のためにがんばっています。
「大人になっても努力し続けます」って宣言しているところが素晴らしいです!「人生は自分で決めるもの」という言葉も素敵です。
〇私は学ぶのは自分の夢のためだと思います。学ばなければ夢が叶えられないと思います。勉強しないと特別な資格をもつ人にもなれないし、学ばないと得られないものもあります。
この児童は、きっと「夢」をもっているんですね。特別な資格が必要な夢なのでしょうか?学ばないと得られないもの、たくさんありますね。
〇私の考えは余裕をもって青春するためです。校長先生は「答えは人による(人によって違う)」と言いましたが、私の答えはこれで、ぜひ友達の意見も知りたいと思いました。
「青春!」よい響きですね。「余裕をもって」というところを詳しく聞いてみたいです。ぜひとも、友達同士で意見交換してみてください。
児童たちが校長の話をよく聞いてくれて、よく考えてくれたことが伝わってきました。
子どもは大人が真剣に話すことをよく聞いて、大人が考えている以上によく考えてくれます。
職員には校長からあらためて「先生方の考えを児童たちに伝えてください」とお願いしています。
この「校長日誌」を読んでくださった方も、身近な子どもたちに「人はなぜ学ぶのか?」を真剣に語ってみてはどうでしょうか?
大人たちみんなで、子どもたちの夢を育てていきたいと思います。
「人はなぜ勉強するのか?」について、10月の校長日誌に書きましたが、今回はその第2弾です。
前期終業式で校長から「人はなぜ勉強するのか?」という話をしました。
私にとって勉強というのは楽しんだり、感動したりするためにやるもの。
そして、私が考える小学生が勉強する理由として、「勉強することで自分のやりたいことがわかるんじゃないかな?」と話したのですが、私の話を児童たちはどう受け止めてくれたのか気になっていました。
その後、本校の放送委員会(児童の委員会)が「わたしたちはなぜ学ぶのか?」というアンケートを全校児童対象に取ってくれました。その結果が11月17日の児童集会で発表されました。
中央小の児童が考える勉強する理由、気になります・・・。
上位5位を発表しましょう。
第5位 「わからないと恥ずかしいから」
小学生らしいといえば小学生らしいですね。
第4位 「よい学校、よい会社に入って、お金を儲けるため」
う~ん、やはり、この考えはあったか! 否定はしませんが・・・
第3位 「いろいろ知っていると役に立つから」
豊富な知識はこれからの人生で役に立つはずですね。
第2位 「読み・書き・計算ができないと困るから」
そうです。基礎的な学力は絶対に必要です。
そして、ダントツの第1位は、「なりたい自分になるため」でした。
多くの児童が「わたしたちはなぜ学ぶのか?」を真剣に考えてくれたことを、たいへんうれしく思います。そして「なりたい自分になるため!」と答えた児童の多くは、きっと「なりたい自分」をもっているのでしょう。
「なりたい自分」のイメージをもち、「なりたい自分」になるために学び、「なりたい自分」になるために努力することのできる児童を応援し、育てていきたいと思います。
11月5日(水)は、小見川中央小学校の今年度2回目の学校公開でした。
7月の学校公開に続き、多くの保護者の皆様、地域の皆様に来校していただき、時間帯によっては教室が満員状態でした。
お忙しい中、お時間をつくって来校してくださったことに感謝申し上げるとともに、学校への期待の大きさを感じ、あらためて身の引き締まる思いもしています。
7月の学校公開は、通常の授業や生活の様子を参観していただくのが主でしたが、今回は多くの外部講師に来校していただき、次のような特別授業を実施し、日常の授業とは一味違う体験ができた一日でした。
○1年生・・・・・「昔遊び教室」 講師:地域のボランティア
「親子ヨガ教室」 講師:ヨガインストラクター
○2年生・・・・・「防犯教室」 講師:千葉県警 よくし隊 あおぼーし
○3・4年生・・・「人権教室」 講師:人権擁護委員
○4・5年生・・・「ネット安全教室」 講師:eネットキャラバン
○6年生・・・・・「平和講演」 講師:ピース・スタッフ
6年生の「平和講演」は、終戦時に小学校3年生だった講師による戦争体験を聞くものでした。今年は戦後80年、児童たちの祖父母の世代も戦争を知らない時代になって久しいですが、「戦争は絶対にしてはいけない」という講師のメッセージは、児童たちの心に深く刻まれたことと思います。紛争が絶えない世界ですが、平和の大切さを児童たちに感じさせていきたいと思います。
余談ですが・・・
私的には、1年生の「親子ヨガ教室」のインストラクターの先生が、私が20代の頃の教え子で、久しぶりの再会と成長された姿に教員としての喜びを感じた一日でした。
本日(10月10日)、全校児童が参加する終業式が体育館で行われ、児童の代表3名(2・4・6年生)が「前期を振り返って」と題する作文を発表しました。2年生の児童は「学校が大好きです!」と発表してくれて、とても嬉しく思いました。4年生は「苦手なことにも挑戦したこと」を、6年生は「運動会で、担任の先生に勧められた応援団をやってみて楽しかったこと」を発表してくれました。
私は半年前の始業式で、中央小を「昨年度以上に笑顔あふれる学校にしよう」「みんながチャレンジできる学校にしよう」という話をしましたが、発表した児童のように、苦手なことや嫌いなことから逃げずに、何にでもチャレンジしている児童の姿が多くみられた前期だったと思います。
校長からは「人はなぜ勉強するのか?」という話をしました。
実は、「どうして勉強しないといけないの?」という児童からの問いに対する先生の考えを児童たちに伝えてほしいというお願いを、2週間ほど前に本校の教職員にしていました。以下は、本日の終業式で校長から児童たちに伝えた「勉強する理由」です。
6年生はもうすぐ修学旅行ですが、箱根や鎌倉について調べていますよね?
校長先生は旅行するのが好きです。旅行の計画を立てるのも好きで、旅行に行く前に訪れる場所の歴史などを調べたりします。美術館に行くなら、そこにある作品を行く前に調べたりもします。
これが楽しいんですよ!
そして実際に行って実物を見てみると、感動が大きいんです。
この「調べること」ってことが、勉強なんです。
だから、校長先生にとって、勉強というのは楽しんだり感動したりするためにやるものだと思っています。
じゃあ、小学生が勉強する理由は何かな? これはみんなが考えてください。
校長先生が考える小学生が勉強する理由は、勉強することで「自分のやりたいことがわかる」ってことだと思います。勉強しないと、自分が何をしたいのかもわからないんじゃないかと思います。
もちろん、正解(答え)は一つではありません。
人が勉強する理由は、人によって違っていていいんです。そして、その理由は今と中学生になってからでは変わっていくと思います。大人になったら、また変わると思います。皆さんも今の自分が納得する、自分にとっての「勉強する理由」を見つけられるといいと思います。
「小学生を相手に、また難しい話をしてしまった・・・」と、終業式が終わって、体育館から教室へ戻る児童たちを見送っていたら、2年生の男子が校長に近づいてきて、こう言いました。
「校長先生の考えと僕の考えは一緒です。」
わかってくれてありがとう!
たくさん勉強して、自分のやりたいことを見つけていこうね!
佐原市、小見川町、山田町、栗源町が合併し誕生した香取市は、令和8年3月27日で20周年を迎えます。香取市では、小学生に「香取市の未来」と題する作文を募集しました。テーマは「20年後の未来はどうなっているか、どのような姿になってほしいか、将来に向けて自分が取り組んでいきたいこと」等です。
中央小の児童の作文を読んで、子どもたちの素直で前向きな気持ちや深い地元愛に感動しました。本校の児童の作文から、私が印象に残ったところを抜粋して紹介します。
ぼくが通っている小学校のいいところは、大きい子が小さい子にやさしくするところ。
ぼくも2年生になったから1年生と一しょにあそんだり、べんきょうをおしえてあげたりしている。おたがいにやさしくすると、みんながえがおになれると思う。
ぼくは大きくなったらバスケットボールのせん手になって、いまのままかとり市にすみたい。ゆう名なせん手になって、かとり市のいいところを日本中にしょうかいしたい。みんながやさしくしてくれる市だよって。(2年生男子)
小さい子にやさしくすること、大切なことですね。もちろん大人もそうでなければなりません。ぜひとも、有名なバスケットボール選手になって、香取市から香取市のよいところを発信してください。
合ぺいして二十年がたつそうですが、さらに二十年がたつと、わたしは28歳です。そのころは、「花火大会はやっているのかな」と思いました。今は、お父さんとお母さんといっしょに見に行ってますが、「二十年後だったら子どもをうんでいるかな」と思いました。きれいな花火を子どもにも見せてあげたいです。
わたしのおじいちゃんとおばあちゃんは、のう家で野さいを作っています。今までにさつまいも、じゃがいも、トマト、いちご、えだまめ、さやえんどう、きゅうり、にんじん、大こんをしゅうかくしたことがあります。このような楽しい体けんを二十年後の子どもたちもできたらいいだろうなと思います。(3年生女子)
20年後はお母さんになっているかも知れませんね。大好きな花火大会に野菜作り、変わってほしくないものが多くあります。そして、安心して子育てができる町であってほしいです。
わたしの家では、毎日のごはんに香取市のお米を食べています。田んぼが広がる風景を見ながら学校へ行くと、四季のうつりかわりを感じることができます。春にはあやめがさいて、夏にはセミの声、秋は金色の田んぼ、冬はカモの群れ。そんな自然がすぐそこにある香取市がわたしは大好きです。
二十年後、わたしは三十歳になっています。今よりももっとにぎやかであたたかい町になった香取市で子育てをしているかもしれません。わたしは人と人、町と町、そして未来と今を結んでいけるような人になりたいです。香取市がこれから二十年先も笑顔とやさしさにあふれた町であるように、自分の手で少しでも関われたらいいなと思っています。(5年生女子)
食べ物は美味しいし、季節を感じる自然豊かな香取市、私も大好きです。(私も香取市で生まれ、大学の4年間以外は香取市に住んでいます。)この児童も20年後にはお母さんでしょうか?笑顔とやさしさであふれた町であるために、子どもたちに負けず、私たち大人も自分にできることをやっていきたいと思いました。
44日間の夏休みが終わり、児童たちは9月1日から登校、学校生活が再開して3日が経ちました。今年の夏は、昨年の猛暑の記録を更新する暑さでしたが、多くの児童たちは健康や安全に気をつけて、元気に充実した夏休みを過ごすことができたようです。今日も教室から元気な声が聞こえてきます。
夏休み前集会では、児童たちに「夏休みにしかできない体験をしよう」と話しました。休み時間に廊下で会うと、「おばあちゃん家に泊まった」とか、「家族で旅行に行った」とか、楽しい夏の思い出を話してくれる児童、廊下に展示してある夏休みの作品の説明をしてくれる児童が多くいます。久しぶりに会った友達や先生との再会を喜ぶ姿も見られ、学校もまた、児童たちにとって「楽しい場所」、「会いたい人がたくさんいる場所」なのだと校長として嬉しく思っています。
昨日(9月2日)は酷暑の中、6年生の保護者の皆様に校内美化活動に取り組んでいただきました。暑さで体調を崩す方がいないか心配でしたが、校庭がすっかりきれいになりました。夏休み中にはPTA本部役員の皆様に除草作業をしていただいています。学校職員だけではできないことが、保護者の皆様の協力のおかげでできていると感謝の気持ちで一杯です。
まだまだ厳しい暑さは続くようですが、これから学校が最も充実する季節になります。児童の安全・安心を第一に、日々の授業や生活を大切にしながら、各学年の校外学習、遠足・宿泊学習、修学旅行、マラソン大会などの学校行事を充実させていきたいと考えています。
4月の始業式から本日(7/18)まで、授業日数にすると72日(1年生は71日)。
中央小の児童たちは様々なことにチャレンジし、笑顔で学校生活を送ることができました。
本日は体育館で「夏休み前集会」を行い、校長からは次のような話をしました。
みなさんには「長い休みにしかできない体験」をしてもらいたいと思います。例えば・・・、
読書が好きな人は、本を毎日1冊読んでみましょう。夏休みは44日ありますから、44冊読めます。その気になれば、100冊だって読めます。
スポーツが好きな人は、その種目に集中して取り組んでみましょう。でも、熱中症には気をつけて!
普段はあまり会えない、おじいちゃん、おばあちゃん家に泊まってたくさん話をする、なんていうのも、長い休みにしかできない体験です。
ところで、皆さんは「となりのトトロ」って知ってますか?
「もののけ姫」は? 「魔女の宅急便」は? では、「千と千尋の神隠し」は?
今、校長先生が言ったのはアニメ映画のタイトルで、どれも作った人(監督)は同じ人です。
ぜんぶ、宮崎 駿 監督 が作った映画です。
宮崎 駿 監督は、小学生の夏休みに家族で田舎を訪れたそうです。そして、普段住んでいる町とは違う自然豊かな風景や昆虫との触れ合いから大きな影響を受け、それが大人になってからの映画づくりに活かされたそうです。つまり、子どもの時の体験がなければ「トトロ」は生まれなかったんです。
みなさんも、この夏、自分の人生を変えるような出会いがあるかもしれません。
熱中症や事故にはくれぐれも気をつけて、たくさんの体験をしてください。
児童たちが下校した後の職員打合せで、中央小の先生方には次のような話をしました。
先生自身も「長い休みにしかできない体験」をしてください。
そして、夏休み明けに児童たちに、その話をたくさんしてあげてください。
よく働き、人生を楽しむ・・・「よい大人のモデル」を児童たちに示してください。
そう言ったからには、私も「長い休みにしかできない体験」をしなければいけないな・・・と思いながら、9月1日に成長した児童たちや先生方に会えるのを楽しみにしています。
小見川中央小学校は、明治7年に創立され、今年度152年目を迎えた伝統のある学校です。学校はかつて舟運の河港として栄えた小見川市街に位置し、学区は歴史的にも北総の文化拠点として発展するとともに、黒部川が流れる豊かな自然に囲まれ、数多くの商店・住居・施設等を有する地域です。
平成30年度からは旧小見川南小と統合し、スクールバスによる通学が始まるなど、地域の教育を担う拠点校として新たなスタートを切りました。
本校の教育目標は、「自分の良さや可能性を実感できる子どもの育成」です。
児童一人一人が、学校生活の中で、成功体験を積み上げていくことにより、「自分にはこんな良いところがある」という自分の良さや、「自分もやればできる」という自分の可能性、さらに「できるようになった」という自分の成長を実感させていきたいと考えます。
令和6年度の児童対象の学校評価アンケートでは、「先生方は、がんばったときに、ほめたり、認めたりしていますか」という設問に対し、「十分あてはまる」「ほぼあてはまる」と回答した児童は、前年度より増加し95%でした。
今年度も教職員が児童の「よさ」や「がんばり」を認める支援を続けていきます。
また、本校では、めざす子どもの姿を「よく考えてする子ども」としています。
子どもたちは毎日の学校生活で『あ・そ・べ(あいさつ・そうじ・べんきょう)』を合言葉に、笑顔いっぱい・元気いっぱいに学校生活を送り、「笑顔あふれる中央小」を教職員とともにつくっています。
子ども一人一人の心を大切にしながら、地域に愛される温かい中央小になるよう、職員一丸となって教育活動を進めてまいります。
令和7年4月
香取市立小見川中央小学校 校長 久保木 靖
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
上の学校行事は,
カレンダーの右下真ん中のボタンをクリックすると,拡大表示され,内容を見ることができます。
また,月ごとに印刷することができます。
※ コロナウィルス感染拡大予防のため、行事等が変更になる場合があります。