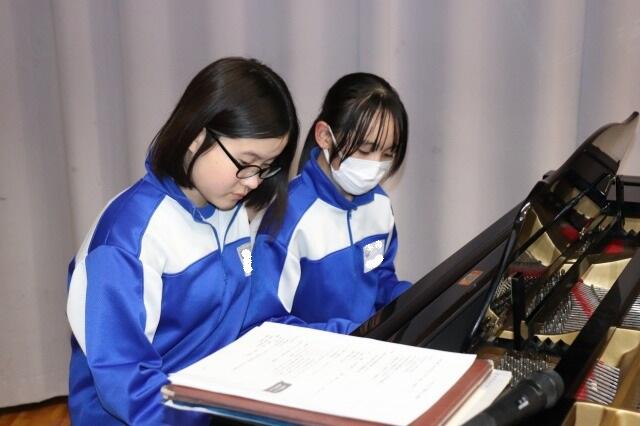文字
背景
行間
北小ニュース
日誌
2月21日(金)音楽集会
2月21日(金)音楽集会の様子をお届けします!
指揮と伴奏は6年生! とっても歌いやすかったですよ。
歌っているのは「雪」。ゆきやこんこ あられやこんこ・・・。


リズム遊び「3時のおやつ」です。リーダーは6年生。リーダーの「3時のおやつは?」の合図で、おやつの形をつくります。写真は、シュークリームとショートケーキ。

6年生が、リズムをとってくれます。

「3時のおやつは?」で示したリーダーのおやつは「シュークリーム」。リーダーと同じおやつのジェスチャーをしてしまったらアウト!

楽しそう!

優勝者は、6年生の2名!!

2回戦! これは、ソフトクリームですね。同じのを出しちゃだめですよ!

2回戦の優勝者!

最後に、創立記念式で歌う「校歌」と「ビリーブ」。
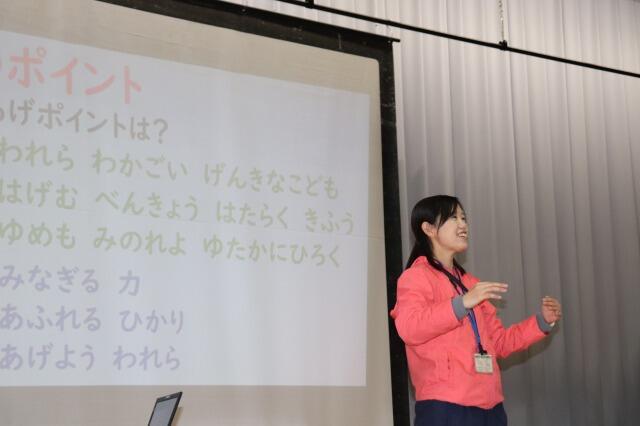
リズム遊びで、心も体もほぐれたからか、口の開け方がさらによくなりました!

創立記念式では、警察音楽隊の演奏に合わせて歌うことができます。楽しみ!!


6年生、いつも片付けまでありがとう!!
学校の予定
バナー
外部リンク
カウンタ
5
4
0
1
4
9
4