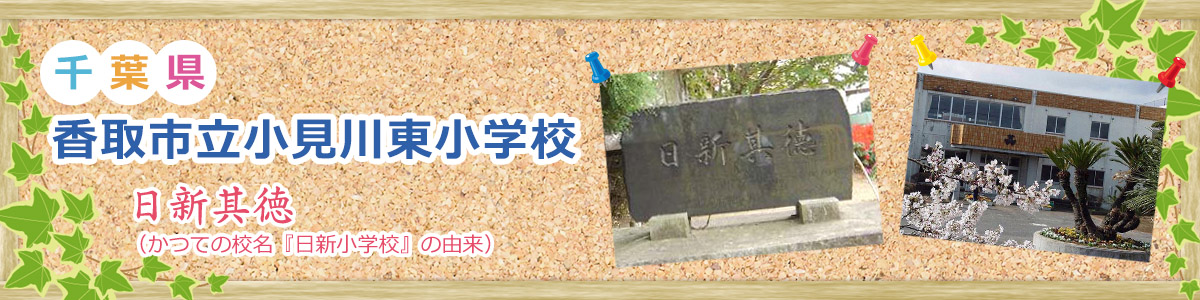文字
背景
行間
「日新其徳」とは
東小学校のかつての名称は,「日新小学校」であった。日新小学校の名称が使われ始めたのは,明治18年1月に阿玉川小学校が廃止され,本校の下飯田小学校と統合された時からである。以後森山国民学校になる昭和16年3月29日の卒業式まで使われた。
「校名が村の名前をとらず,日新ということになったのはよく分かりませんが,知識・教養の書とされた四書の中に『日新其徳』とあり,これから採られた聞いております」
(東小学校百年の歩みP60)
☆広辞苑(岩波)「日々に新しくなること。毎日,旧来の悪いところを改めること。」
☆漢字源(藤堂明保著)「日々に新しくなる。日々に悪いところを改めること。」
「日新たに,又日々に新たなり」
☆大学(諸橋氏)「大学」講義「荀日新,日日新,又日新」(傅二章)
※読み:まことに日に新たに,日々新たに,又日に新たなり
意味:「今日の行いは昨日よりも新しくなり,明日の行いは今日よりも新しくなるように修養に心
がけねばならない。」
殷の湯王は,これを盤,すなわち洗面器の器に彫りつけて毎日の自誡の句とした。
土光敏夫氏はこの「日々新たなり」を好んだ。座右の銘を一つ上げろと言われれば,躊躇なくこの言葉を上げたいという。「一日を一生懸命やるために」「正しき者は強くあれ」の中で,「神は万人に公平に一日二十四時間を与え給うた。」われわれは,明日の時間を今使うことはできないし,昨日の時間を今取り戻すすべもない。ただ,今の時間を有効に使うことができるだけである。・・・私は一日の決算は一日にやることを心掛けている。うまくゆくこともあるが,しくじることもある。しくじれば,その日のうちに始末する。反省すると言うことだ。今日が眼目だから,昨日の尾を引いたり,明日への持ち越しをしたりしない。昨日を悔やむこともないし,明日を思い煩うこともしない。このことを積極的に言い表したのが,「日新」だ。昨日も明日もない。新に今日という一日に全力傾ける。今日一日一日を有意義に過ごす・・・」

創立100周年記念(昭和52年)の時に,建てられました。東門を入ったところにあります。日新小学校の校名の由来も記されています。
新着
1年生の国語では「思い出のアルバム」という単元を学習し、スライドで一年間の振り返りを行いました。なつかしい写真が現れるたびに、「こんなことあったね~」と、教室に笑顔があふれました。2年生の生活科は、「成長した自分を振り返ろう」という単元でした。自分が産まれてからの写真を見ながら、これまでの人生でできるようになったことを振り返りました。歩くことができなかった人が、今では一人で学校に通うことができるようになりました。何よりも健康にすくすくと育っています。お家の方に感謝しなければいけませんね。
2月5日(金)に行われる、令和8年度の児童会役員認証式のリハーサルを行いました。流石ですね。バッチリでした!
昨日から2月がスタート。お正月からもう1か月が過ぎたのですね。1月は「行く月」、2月は「逃げる月」、3月は「去る月」と言いますから、今後はさらに経過の早さを実感することでしょう。
さて、5年生の理科では、振り子の特徴を捉えるための授業でした。おもりの重さ、糸の長さ、振り幅…、1往復する時間は何によって変わるのでしょうか。東っ子たちの関心は高まっていました。次の実験が楽しみですね。
4年生の英語では、日常生活の表現を学習しました。「歯を磨く」「布団を片付ける」等の英語をくり返し発声し、表現を身に付けました。ジェスチャーで答える場面ではとても盛り上がりました。
※本日「日新其徳」第9号を配付しました。(配付した学校だよりには「第10号」となっていますが、正しくは「第9号」です。申し訳ありません)
(5年生)
(4年生)
{{item.Plugin.display_name}}
{{item.Topic.display_publish_start}}
{{item.RoomsLanguage.display_name}}
{{item.CategoriesLanguage.display_name}}
{{item.Topic.display_summary}}
アクセシビリティ
文字
背景
行間
カウンタ
3
5
9
8
3
2
2
家庭でできる学習サイト
「ちばっ子チャレンジ100」
(千葉県教育委員会:学習資料)

子供の学び応援サイト(文部科学省)

NHK For School(NHK)
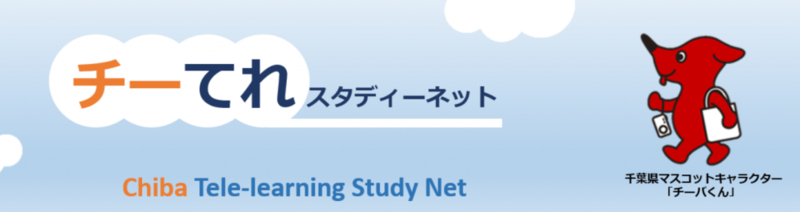
チーてれスタディーネット
(千葉県教育委員会)
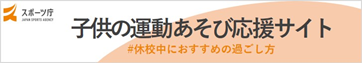
子供の運動あそび応援サイト
(スポーツ庁)
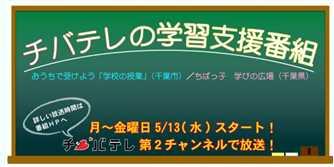
チバテレの学習支援番組

家庭での体育、保健体育の
学習コンテンツ参考例
県内トップ・プロによる家庭(室内)で出来る運動動画集
リンク